認知症はジワリジワリと進んでいきます。介護を続ける中、いつの間にか介助の手間が増え、理不尽な訴えが続く日々に感情面でのストレスもたまっていませんか?「施設入所」は寝たきりや歩けなくなったら考えることと思われがち。でも認知症の場合は安心で快適な環境で元気な暮らしを長く続けるために選択します。
この記事では、施設入所のタイミングについて、認知症の母の介護の中での経験を交えながらご紹介します。
お困りの方はぜひ最後までご覧ください。
施設入所は”かわいそう”?
「できることなら、ずっと住み慣れた我が家で暮らしてほしい」
誰もがそう願うものです。だからこそ、施設への入所に迷いや抵抗を感じるのは、ごく自然なことです。特に認知症の場合は歩行も十分可能な場合が多く、私も「親を施設に預けるなんて…」と罪悪感を抱え、母の入所後も暫くの間は心が揺れました。
今年5月、母は天寿を全うしました。振り返ってみて、私は今、「施設入所という選択は、間違っていなかった」と心から思っています。
病院勤務を通し、高齢者の転倒は骨折につながり、それがきっかけで寝たきりや肺炎、尿路感染を引き起こし、命にかかわるケースが多いということを知っていました。

自宅での生活は、リフォームで手すりをつけたり段差をなくすなどしてあっても、やはり十分ではなく、トイレまで距離もあります。
母は認知症が進み注意も行き届かなくなっていたので、在宅では常に心配が尽きませんでした。

でも、施設での暮らしで、転倒が避けられ、排泄がより長く自立し、食事も他の入居者と一緒にとるなど、人との関わりの中で暮らしの質を保ち続けられたのです。「施設に入ってからのほうが、母はよく笑うようになった」そんなふうに感じた日もありました。
施設入所で母の寿命が伸びたとさえ感じるのです。
認知症の介護は長丁場です。
施設入所は「最後の手段」ではなく、「新しいケアの形」。
プロの手による安全で安定したケア環境は、ご本人にとっても安心で快適な暮らしをもたらします。
そして、介護者が少し肩の力を抜いて「家族」として向き合える時間を取り戻すことにつながります。
無理をしすぎず、必要なときに必要なサポートを受けることが、よりよい介護にもつながります。ご本人もご家族も、笑顔で過ごせる時間が少しでも増えるように、今できる選択をしていきましょう。
施設入所には、介護者・本人の両方にとって大きなメリットがある一方で、注意しておきたいデメリットもあります。以下にわかりやすく整理しました。
施設入所のメリット
1. 安全な生活環境が整っている
・転倒・徘徊・火の不始末などのリスクに24時間体制で対応
・(医療) 介護のプロが常駐しており、急変時にも安心
・施設が転倒しにくい作りになっている
2. 介護の専門職による質の高いケアが受けられる
・食事・入浴・排泄などの介助を専門職が実施
・認知症に理解のあるスタッフが対応してくれる
3. 家族の身体的・精神的負担が軽減される
・在宅介護による疲弊や共倒れを防げる
・家族は「介護者」から「家族の立場」に戻れる
4. 本人にとっての生活の安定
・決まったリズム・日課があることで落ち着いた生活を送りやすい
・レクリエーションや他の入居者との交流がある施設も多く、孤独を防げる
施設入所のデメリット
1. 費用がかかる
・公的施設(特養など)は比較的安価だが、待機が多い
・民間施設は月額費用が高く、入居一時金も必要な場合がある
2. 家庭のような自由が制限される
・外出・外泊・食事の選択などが制限されることがある
・プライバシーが十分でない施設もある(相部屋など)
3. 環境の変化に戸惑う場合がある
・引っ越しや新しい生活に慣れるまでに混乱や不安を感じる人もいる
・「施設に入れられた」という思いを本人が抱く場合も
4. 家族との距離ができる
・毎日顔を合わせられないことで疎遠になったと感じることも
・「最期を自宅で迎えさせてあげたかった」という後悔を持つ人もいる
デメリットのなかで、御本人がさみしいと感じる部分については、出来る範囲でそれを補えるとよいと思います。
私は母の施設入所により、母の訴えや行動で振り回されることが少なくなったことで、毎週日曜日の午前中は母と過ごすと決められました。毎回母は私が来たことも忘れてしまいますが、他の入所者さんやスタッフさんとの会話で思い出させてくれるのです。
こんなときが“入所のサイン”
母は10年前に認知症の診断がついて見守りが始まり、介助が必要になったのが7年前からでした。施設入所は約5年前からですが、決断の山は2つありました。一つは介護している私が決断する時、もう一つは母が施設入所を受け入れる時です。
次のような状況が続いている場合は、入所を前向きに検討しましょう
日常生活が成り立たなくなってきた時
・夜間の徘徊や昼夜逆転で家族の睡眠がとれない
・火の不始末や外出中の転倒など、安全面に不安がある
・排泄や食事の介助が常時必要になり、在宅での対応が困難
介護者の心身に限界がきている時
・自分自身の健康や仕事に支障が出てきた
・感情的になってしまい、自分を責めてしまう
・介護うつや離職の危機に直面している
医療ケアが必要になった時
・薬の管理が難しい
・持病などの慢性疾患が悪化してきた
・認知症以外の疾患で入退院を繰り返している
施設入所を本人に納得してもらうコツ
認知症の方にとって一番の敵は「不安」です。だからこそ、入所を納得してもらうには、
・強制や説明責任を押し付けず
・小さなステップで安心感を積み重ね
・「自分のためなんだ」と感じられるように導く
ことが鍵となります。
1. 正面から「施設」と言わない
🌿「ちょっと体を休めに行こう」「お泊まりのリハビリに行ってみよう」
👉「施設」や「入所」という言葉は避け、「体調を整えるための場所」「お試しの短期滞在」など、柔らかい言葉に言い換えます。
2. 家族が疲れていることを責めずに伝える
🌿「最近ちょっと私、体が疲れてきちゃって…あなたに何かあったらすぐ対応できないから、しばらく安心できるところでゆっくりしてほしい」
👉家族の負担を責めるのではなく、**「大事に思っているからこそ、安心できる環境を用意したい」**という気持ちを伝えることがポイントです。
3. 「一時的」「お試し」という説明にする
🌿「まずは短期間だけ行ってみよう。気に入らなければ戻ってきてもいいから」
👉「ずっとそこに住む」と言うと強い拒否が出ます。「体調を見るため」「リハビリのため」「気分転換」など、期間限定の説明が受け入れられやすいです。
4. 信頼されている第三者からの助言を使う
・かかりつけ医師
・ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員
👉家族の言葉だけでなく、医療や福祉の専門職からの提案として話してもらうと、納得しやすくなります。
5. 施設を「ポジティブな場所」として紹介する
🌿「ごはんも美味しいらしいよ」「同年代の人がいて楽しいみたい」
👉「自分の居場所がなくなる」不安を打ち消すために、楽しみや安心感がある場所として紹介する工夫が有効です。
6. 入所日当日は「デイサービスに行く感覚」で
🌿「ちょっと今日は見学と体験に行ってみよう」
🌿「荷物は後で届けるから、手ぶらで行こうね」
👉大きな決断に見せず、いつもの延長線のように自然に導くことが大切です。
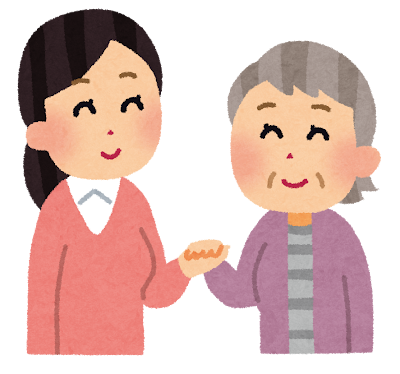
母は、元気な頃からいつかは施設入所になると覚悟していました。デイサービスに通いながら候補の施設をリサーチしていてくれましたが、いざとなるとやはり抵抗がありました。
当地は寒冷地のため冬場の生活が心配だったことと、希望していた施設が人気でしばらく待たなければならなかったため、空いた時を逃すと次はいつになるかわからないという状況が、入所を後押ししてくれました。
また、施設を見学した際に、入所者さん達が”ウェルカムオーラ”を送ってくださったので母も私も安心しました。
まとめ
今回は、施設入所のタイミングと注意点についてご紹介しました。
★認知症の介護は長丁場です
★施設入所は「よりよく生きる」ための選択肢
施設入所は、ご本人にとっては安心で安全な暮らしを支える選択肢であり、介護する家族にとっては**「介護者」から「家族」に戻れる時間を取り戻すチャンス**でもあります。
★施設入所を納得してもらう時は、本人の「不安」より「安心」にフォーカスしましょう
施設入所は「介護の限界」ではなく、「新しい暮らし方」へのステップです。
どうか、「家で頑張り続けなければならない」という思い込みを少しだけゆるめてみてください。在宅介護ではできなかったことが施設では可能になり、ご本人もご家族も心に余裕を持てる暮らしができるかもしれません。
大切なのは、「どんな暮らしを大事にしたいか」をご本人と家族で話し合いながら、その人らしい生活をどう守るかを考えることです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
少しでもご家族の介護負担が軽くなり、御本人との残された時間を悔いのないように送っていただけますように。
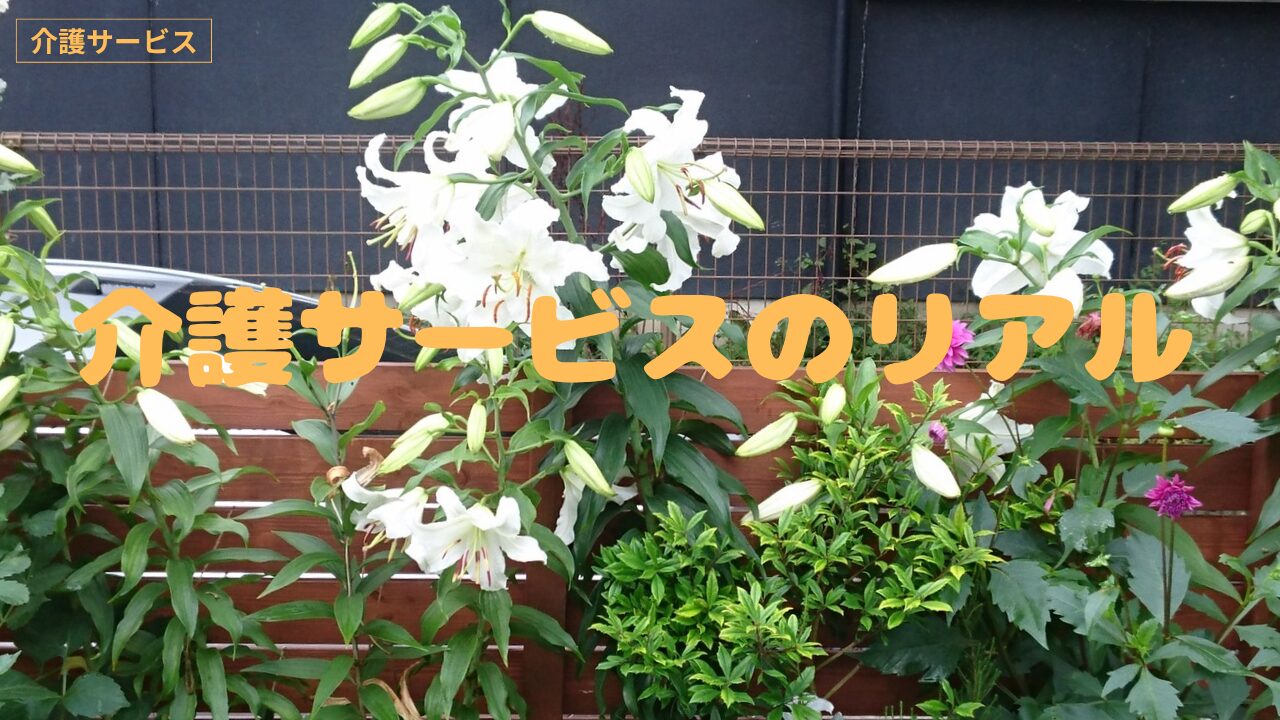



コメント